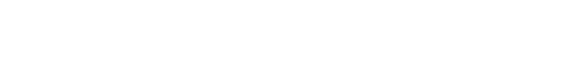吸湿式ハイグロマスターの特徴と仕組み
こんにちは。墨田トータルサービス株式会社の田邊です。
今回は、吸湿式の圧縮空気除湿装置(エアドライヤー)の特徴と仕組みについて、お話できればと思います。
工場にとって、湿気は非常に厄介な課題です。設備の故障を引き起こし、製品の品質を低下させるなど、多くのトラブルの原因となります。だからこそ、空気中の水分を除去する除湿装置は、欠かせないものとなっています。
その中でも、吸湿式エアドライヤーは、高度な除湿や低露点が求められる用途で広く使用されています。
ですが、「吸湿式のエアドライヤー」という言葉を聞いたことがあっても、その具体的な仕組みについては想像しづらい、という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、吸湿式エアドライヤーの基本的な仕組みと特徴に加え、その利点についてご紹介します。「特定の産業や分野において、なぜ吸湿式が選択されるのか?」という疑問にお応えします。
導入の際は、現調に基づいて最適なものを私共から改めて提案させていただきますが、二つの除湿方法の違い、選択の指針について、皆様の判断の一助になればと思います。
圧縮空気脱湿脱油装置の導入・変更をご検討中の方は、以下のボタンからお問い合わせください。
吸湿式エアドライヤーとは?
圧縮空気中の水分を吸湿することによって除湿するタイプのものが、吸湿式エアドライヤーと呼ばれます。「吸着式」とも呼ばれ、冷却式エアドライヤーとは別のものとして区別されます。
原理としては、乾燥剤をイメージしてもらうのがわかりやすいです。吸湿材(吸着材とも)に空気中の水分を吸着することによって、圧縮空気を乾燥させます。
対して冷却式は、冷やすことによって結露させた水分を取り除くことで、除湿を行います。
このように、吸湿式エアドライヤーと冷却式エアドライヤーは、除湿の方法によって区別されます。
使用される吸湿材は再利用可能であり、その再生方法によってさらにさまざまな形態に分かれます。
弊社取り扱い製品、ハイグロマスターシリーズにおいては、C型の三種類が吸湿式エアドライヤーに該当します。
吸湿式エアドライヤーの特徴
吸湿式エアドライヤーは、「冷却式エアドライヤーよりも低露点の空気を得られる」のが特徴です。
除湿方式によるメリット
吸湿式エアドライヤーは、乾燥に吸湿材を用います。その仕組み上、吸湿材が乾燥している状態であれば、空気中に含まれる水分がごく少量であっても吸着させることができます。
冷却式に比べ温度の影響を受けづらいため、高度な乾燥が求められたり、温度の変化が激しい条件下で運用できるという利点があります。
具体的には、低露点(圧力下露点温度-20℃DP以下)が求められる場合などが挙げられます。
吸湿式エアドライヤーを使用する産業・分野
吸湿式は、高度な乾燥が求められる場合に選択されることが多い除湿方式です。吸湿式エアドライヤーを使用する産業、分野は、以下のようなものが挙げられます。
電子機器・半導体製造業
半導体製造や電子機器の組立工程では、湿気が製品の品質や性能に直接影響を与えるため、低露点の乾燥空気が必要です。
医薬品・製薬業界
医薬品の製造や保管において、湿度管理は製品の品質保持に不可欠です。
食品加工業
食品の乾燥や包装工程において、湿気を除去するために使用されます。
化学工業
化学反応や製造過程において、湿度管理が重要な場面で利用されます。
自動車産業
塗装ブースや乾燥炉での湿度管理に使用されます。
エネルギー分野(電力・ガス)
発電所やガスプラントでの湿度管理に利用されます。
倉庫・物流業界
湿気に敏感な製品の保管に使用されます。
建築材料(セメント・石膏など)製造
湿気による材料の固結や変質を防ぐために使用されます。
繊維業界
織物や糸の加工過程で、湿度を調整するために使用されます。
吸湿式エアドライヤーの仕組み
吸湿式エアドライヤーについて、もう少し深掘りしてみましょう。
吸湿材の役割
吸湿材には、周囲の空気中の水蒸気濃度と、吸着している水蒸気濃度を、均衡させる性質があります。自身よりも周囲の湿度が高ければ水分を吸着し、低ければ水分を放出するといった形です。
エアドライヤーの運用では、吸湿材が周囲の空気よりも乾いた状態で使用されます。そのため常に、周囲の空気から水分を吸着する形で運用され、除湿し続けることができます。
吸湿材は吸湿式エアドライヤーの除湿において、重要な役割を占めているといえます。
吸湿材の再生
吸湿材はその性質上、ある程度の水分を吸着するとそれ以上の除湿を行えなくなります。周囲の空気に対して、吸着している水分の量が釣り合ってしまうためです。
そのため、一定値まで水分量が上がった吸湿材は、含まれた水分を放出する必要があります。これを「再生工程」と呼びます。
吸湿材は使い捨てではなく、何度でも使用できます。
再生方法によるエアドライヤーの分類
吸湿式エアドライヤーは、吸湿材の再生方式によって二つに分類されます。
加熱式
空気を温めることによって吸湿材を乾燥・再生するのが、加熱式です。加熱には、主にヒーターやボイラーなどが用いられ、必要に応じてブロワーも使われます。
メリットとして、低露点の実現や連続運転に適し、より高性能で安定した除湿を行うことができる点が挙げられます。
反面、デメリットとしては、加熱装置による装置の大型化や初期費用などが挙げられます。
非加熱式
加熱減を使わずに吸湿材を再生するのが、非加熱式です。「ヒートレスドライヤー」とも呼ばれます。
圧縮空気の膨張を利用して体積あたりの湿度を低下させ、それによって除湿を行います。
非加熱式のメリットは、設備そのものをコンパクトに収めることができること。それによって、コストを抑えられる点です。加えて、水分は大気へ放出されるため、ドレン処理も不要となります。
デメリットとしては、エアーのロスが大きくなってしまうことが挙げられます。また、より低い露点が求められる場合、再生に使用するブロー量が増えてしまうため、省エネルギーでの運用は難しくなります。
まとめ
吸湿式エアドライヤーは、高度な除湿性能を特徴としています。低露点の空気が求められる産業や、特定の用途で使用されます。吸湿材の特性を活かした除湿方式によって、冷却式が適さない環境、ニーズにも対応することができます。
一方で、加熱式と非加熱式の選択には、それぞれの特性や運用コストを考慮する必要があります。
湿気対策は、製品の品質向上や、設備の長寿命化に直結する重要な要素です。導入を検討する際は、求められる露点や運用環境に応じて最適なエアドライヤーを選びましょう。
エアドライヤーの導入をご検討中でしたら、ぜひ一度、お問い合わせください。お客様のご要望と現場の環境にあわせて、最適な商品をご提案いたします。